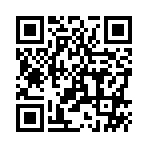今日は朝一番で「しょならさん」参り。
気になっていた修那羅山安宮神社(筑北村)の
石神仏たちに会いにいってきました。
江戸時代”最後の修験者”といわれる修那羅大天武さんが開いた神社境内には、
あの佐久間象山はじめ、信者たちから奉納された石神仏が
実に800以上、祀られています。
その一部は、長い年月を経て、丸ごと苔に覆われ、
雨風にも浸食され、ほぼ森と一体化しているご様子。

「なんか…こわ」と思う人もいるかもしれません、が、
この石神仏さまが実にユーモラスなのです。
神仏習合や民俗信仰のものをベースに、
庶民感覚で自由に神仏を作っちゃってる感じ。
そこに、当時の人々の素朴な祈りや願いが見えてくるようです。

よい酒が出来ますように。お酒の神様、酒泉童子。
お酒好きとして思わず手を合わせる。

五穀豊穣の気持ちはすごく伝わってきますが、「一粒万倍神」て。笑
言霊神様シリーズは他にも「山之神」とか「縁結神」とかおられましたが、
やはりナンバー1はこちら。

「催促金神」
貸した金、返せよ神ってことですね。笑
神様に祈りたいほど、よっぽど延滞されていたのでしょうか。

こちらは、もはやなんの石神仏かわからない。
ピュアスマイルおかっぱ少女に、心ほっこり。
どこかコミカルで、ユルさも香るクオリティは、
庶民が仏師のようなプロではなく、
村の石屋さんなどに頼んだものが多いから。
そんな話もお聞きしました。
百年あまり前の人々も、今と同じように日々の中で
一喜一憂し、時に、想いを神仏に託していたのだなあ。
古の祈りの形の一端に触れられた、よき時間でした。

さて。さらに遡って、、、およそ5000年前。
今の信州にいた人々は、これをどういう気持ちで作っていたんでしょ。
おんなじように、そういう想像を巡らす時間が楽しい縄文見物でありまス。
Posted by 小林新 at
23:12